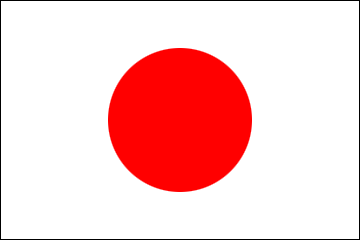明治のネパール人留学生 ー はじめに
令和3年2月17日
栗、菊、柿1そして藤は、ネパールのカトマンズでもそれぞれ大きめのKattus、Godavari-phool、Haluwabed、そしてNil-laharと呼ばれ、人々のあいだでよく知られた花・果物である。これらはいずれも、日本では何百年もの以前から、ごく普通に見られる植物である。しかし、藤や菊の花の美しさや柿や栗の美味しさは、20世紀のはじめまでネパールでは馴染みのないものだった。これらはすべて、今から100年前に日本での勉学を終えて母国に帰ったネパールの若者たちが持ち込んだものなのである。この若者たちこそが、ネパールから日本に渡った最初の留学生だった。彼らは持ち帰った花や果物の種子を貴族の家の庭に植えた。そればかりでなく、若者たちは日本で学んだ専門的な知識をも祖国に持ち帰ったのである。
20世紀初頭、アジアを含めた世界中の国々が西側諸国に学生を送り込み、近代化を学び取ろうとしているときに、ネパールは若者たちを日本に送り、兵器製造、機械工学、鉱山学、農業、応用化学、そして製陶術の分野で進んだ技術を学ばせた。しかし、その後ネパールでは、近代化の努力をうまく推し進めることができなかった。国の発展に必要な安定した政治と平和は維持されていたものの、それは封建制度という枠組みのなかであった。104年間にわたるラナ家(日本での将軍家にあたる)による平和な支配のあいだに、将来に対する明確な考えと意志さえあったならば、政府はさまざまな開発計画を実施することができたはずだ。しかし、実際には、この100年余りものあいだ、ネパールは世界から孤立した状態にあったのである。
1846年から1951年にかけて、ラナ家は階級的な支配制度を確立し、ネパールに君臨しつづけた。この間、国王の主権は敬意をもって認められてはいたものの、実際の権威はいくつかの儀式を司ることだけに限られていた。実質的な国の支配者は首相であり、首相も他の大臣職もラナ家の人間で占められていた。そうした国王と首相の関係は、1603年から1867年まで続いた日本の江戸時代における、天皇と徳川将軍の関係に類似しているといえる。この期間、日本でも鎖国政策がとられていた。
ラナ家が勃興した背景には、1775年から1846年にかけてネパールを支配した不安定な宮廷政治がある。ラナ家の前身であるクンワル家やタパ家、パンデ家、バスニャト家といった一族出身の人たちが、宮廷政治でさまざまな役割を果たしていた。度重なる動乱のために政治は不安定になり、中央の権威は弱体化した。ラナ家を創設したジャンガ・バハドゥルはクンワル家の出である。ジャンガ・バハドゥルは一介の陸軍大尉から、わずか29歳にして首相にまで上りつめた。1846年から77年に亡くなるまで、ネパールに君臨したのである。ネパールが当時インドを支配していた英国東インド会社の領地にならずにすんだのも、彼の働きがあったからである。
ネパールのジャンガ・バハドゥルも日本の豊臣秀吉も、底辺からトップに上りつめた人物である。両者とも国の全土に支配を及ぼした。秀吉はごく普通の足軽で、ジャンガ・バハドゥルは陸軍大尉だった。
歴代のラナ首相のなかには、国民の生活を改善する努力をした人もいた。しかし、改革を施そうとするたびに激しい反発にあい、ライバルである兄弟や従兄弟たちに首相の地位を奪い取られてしまうのが常だった。
そうしたなかで、デヴ・シャムシェル・ラナ首相は慈悲深く進歩的で、自由を愛する最初の支配者だった。彼には豊かな教養があり、さまざまな改革を実施した。カトマンズの南にあるナックーの兵器庫を大々的に改良し、万人への教育を唱えて全国に300の小学校2 を開校する指示を出し、ネパールで最初のニュースメディアである「ゴルカパトラ」3 (大きな発行部数を誇る政府系日刊紙)を発行し、そして、奴隷制度廃止のために働きかけ、他のさまざまな社会福祉事業を行なった。1901年に彼が始めたカトマンズ市民に正午を知らせる大砲の音は、1989年まで毎日欠かさず鳴りつづけた。さらに、さまざまな分野の代表からなる顧問委員会を設置し、国王の下に議会制度を開くことさえしばしば口にした。デヴ・シャムシェルはつねに国民の生活が向上することを念頭に置き、そのための開発プログラムに資金を出したりもした。カトマンズのタパタリにあるデブ・シャムシェルの自宅には議会ホールがあり、人々の代表が集まって会議を開いた。デブ・シャムシェルのひ孫にあたるヒマラヤ・シャムシェル・ラナによると、この会議には初めて下層階級の代表が出席したという。おそらく、それはデブ・シャムシェルが心に描いたような議会だったのであろう。
もう一人の進歩的考えをもった首相であるパドマ・シャムシェルも教育や行政、地方自治、司法の独立、そして他の福祉計画を奨励し、改革を施そうと試みた。こうした発想はよかったのだが、彼は政治力と指導力に欠けたため、辞任をしなければならなかった。
上にあげたことはデヴ・シャムシェルが始めた改革の一部にすぎない。改革をうまく進めるには、技術を身につけた人間と、先進諸国の進んだ知識や技術が不可欠である。それをどう獲得しようかと思案していたところ、彼はカトマンズを訪れていたインド人の旧友スワミ・プラナンダ・ギリに会う機会があった。ギリはアメリカや日本をはじめとする多くの先進国を旅しており、デヴ・シャムシェルにとくに日本を賛辞する話しをした。スワミ・プラナンダ・ギリは、インドの偉大な哲学者であり改革者でもあるスワミ・ビベカナンダの信奉者であると言われている。ビベカナンダは、1893年にシカゴで開かれた世界宗教会議でヴェダンタを説いたことで有名になった。スワミ・プラナンダは彼の"グル"であるビベカナンダと、さまざまな国を旅したものと思われる。
デヴ・シャムシェルは、日本が農業中心の封建社会から産業国家へと急速に転換し、たくさんの中小企業や技術学校を設立したことに感銘を受けたのだろう。こうした日本の動向がネパールの発展にも役立つと考えたのか、8人の留学生を日本に送ることに決め、スワミ・ギリに彼らの案内役として付き添うように頼んだのである。しかし残念なことに、デヴ・シャムシェルは在任期間中に、その計画をやり遂げることができなかった。彼はあまりにも自由にすぎたのである。ラナ一族のなかのライバルたちは、彼の進歩的な考え方を危険視した。その結果、19014年6月27日に、おそらく国内外からの支持を得て、弟であるチャンドラ・シャムシェル・ラナがデヴ・シャムシェルに対する無血クーデターを行ない首相の地位を奪ったのである。デヴ・シャムシェルはわずか114日間在任しただけで首相の席を追われ、ダンクタに行った。その後、西ネパールに近いインドの丘陵地帯ムッソリーで晩年を送ったのである。
デヴ・シャムシェルは弟のチャンドラ・シャムシェルの陰謀を見抜いていたと言われている。しかし、彼は国民は自分の自由な政治思想を支持するだろうと信じていた。国民の支持さえ獲得することができれば、ライバルたちも彼に反する動きをすることはないだろうと考えた。そう信じて、改革計画を推し進めたのである。
1901年から29年まで首相を務めたチャンドラ・シャムシェル・ラナは、万人に教育の機会を与えるという考え5や社会を改革するためのプログラムには反対であったが、ネパールにおけるラナ家の支配を確固としたものにした、抜け目のないい支配者であり行政官でもあった。チャンドラ・シャムシェルはデヴ・シャムシェルが手をつけたいくつかの改革プログラムを実施した。8人の若者が日本に行くことも許可した。日本がアジアの強国となりつつあることに気づいていたのである。彼は1903年に、ネパールを二度目に訪れた河口慧海にも会っている。河口慧海はネパールを最初に訪れた日本人である。このとき、チャンドラ・シャムシェルは河口に「日本をこれほどまでに強くしたのは、何なのか」と質問した。河口は「教育、そして愛国心だ」と答えた。6
20世紀初頭、アジアを含めた世界中の国々が西側諸国に学生を送り込み、近代化を学び取ろうとしているときに、ネパールは若者たちを日本に送り、兵器製造、機械工学、鉱山学、農業、応用化学、そして製陶術の分野で進んだ技術を学ばせた。しかし、その後ネパールでは、近代化の努力をうまく推し進めることができなかった。国の発展に必要な安定した政治と平和は維持されていたものの、それは封建制度という枠組みのなかであった。104年間にわたるラナ家(日本での将軍家にあたる)による平和な支配のあいだに、将来に対する明確な考えと意志さえあったならば、政府はさまざまな開発計画を実施することができたはずだ。しかし、実際には、この100年余りものあいだ、ネパールは世界から孤立した状態にあったのである。
1846年から1951年にかけて、ラナ家は階級的な支配制度を確立し、ネパールに君臨しつづけた。この間、国王の主権は敬意をもって認められてはいたものの、実際の権威はいくつかの儀式を司ることだけに限られていた。実質的な国の支配者は首相であり、首相も他の大臣職もラナ家の人間で占められていた。そうした国王と首相の関係は、1603年から1867年まで続いた日本の江戸時代における、天皇と徳川将軍の関係に類似しているといえる。この期間、日本でも鎖国政策がとられていた。
ラナ家が勃興した背景には、1775年から1846年にかけてネパールを支配した不安定な宮廷政治がある。ラナ家の前身であるクンワル家やタパ家、パンデ家、バスニャト家といった一族出身の人たちが、宮廷政治でさまざまな役割を果たしていた。度重なる動乱のために政治は不安定になり、中央の権威は弱体化した。ラナ家を創設したジャンガ・バハドゥルはクンワル家の出である。ジャンガ・バハドゥルは一介の陸軍大尉から、わずか29歳にして首相にまで上りつめた。1846年から77年に亡くなるまで、ネパールに君臨したのである。ネパールが当時インドを支配していた英国東インド会社の領地にならずにすんだのも、彼の働きがあったからである。
ネパールのジャンガ・バハドゥルも日本の豊臣秀吉も、底辺からトップに上りつめた人物である。両者とも国の全土に支配を及ぼした。秀吉はごく普通の足軽で、ジャンガ・バハドゥルは陸軍大尉だった。
歴代のラナ首相のなかには、国民の生活を改善する努力をした人もいた。しかし、改革を施そうとするたびに激しい反発にあい、ライバルである兄弟や従兄弟たちに首相の地位を奪い取られてしまうのが常だった。
そうしたなかで、デヴ・シャムシェル・ラナ首相は慈悲深く進歩的で、自由を愛する最初の支配者だった。彼には豊かな教養があり、さまざまな改革を実施した。カトマンズの南にあるナックーの兵器庫を大々的に改良し、万人への教育を唱えて全国に300の小学校2 を開校する指示を出し、ネパールで最初のニュースメディアである「ゴルカパトラ」3 (大きな発行部数を誇る政府系日刊紙)を発行し、そして、奴隷制度廃止のために働きかけ、他のさまざまな社会福祉事業を行なった。1901年に彼が始めたカトマンズ市民に正午を知らせる大砲の音は、1989年まで毎日欠かさず鳴りつづけた。さらに、さまざまな分野の代表からなる顧問委員会を設置し、国王の下に議会制度を開くことさえしばしば口にした。デヴ・シャムシェルはつねに国民の生活が向上することを念頭に置き、そのための開発プログラムに資金を出したりもした。カトマンズのタパタリにあるデブ・シャムシェルの自宅には議会ホールがあり、人々の代表が集まって会議を開いた。デブ・シャムシェルのひ孫にあたるヒマラヤ・シャムシェル・ラナによると、この会議には初めて下層階級の代表が出席したという。おそらく、それはデブ・シャムシェルが心に描いたような議会だったのであろう。
もう一人の進歩的考えをもった首相であるパドマ・シャムシェルも教育や行政、地方自治、司法の独立、そして他の福祉計画を奨励し、改革を施そうと試みた。こうした発想はよかったのだが、彼は政治力と指導力に欠けたため、辞任をしなければならなかった。
上にあげたことはデヴ・シャムシェルが始めた改革の一部にすぎない。改革をうまく進めるには、技術を身につけた人間と、先進諸国の進んだ知識や技術が不可欠である。それをどう獲得しようかと思案していたところ、彼はカトマンズを訪れていたインド人の旧友スワミ・プラナンダ・ギリに会う機会があった。ギリはアメリカや日本をはじめとする多くの先進国を旅しており、デヴ・シャムシェルにとくに日本を賛辞する話しをした。スワミ・プラナンダ・ギリは、インドの偉大な哲学者であり改革者でもあるスワミ・ビベカナンダの信奉者であると言われている。ビベカナンダは、1893年にシカゴで開かれた世界宗教会議でヴェダンタを説いたことで有名になった。スワミ・プラナンダは彼の"グル"であるビベカナンダと、さまざまな国を旅したものと思われる。
デヴ・シャムシェルは、日本が農業中心の封建社会から産業国家へと急速に転換し、たくさんの中小企業や技術学校を設立したことに感銘を受けたのだろう。こうした日本の動向がネパールの発展にも役立つと考えたのか、8人の留学生を日本に送ることに決め、スワミ・ギリに彼らの案内役として付き添うように頼んだのである。しかし残念なことに、デヴ・シャムシェルは在任期間中に、その計画をやり遂げることができなかった。彼はあまりにも自由にすぎたのである。ラナ一族のなかのライバルたちは、彼の進歩的な考え方を危険視した。その結果、19014年6月27日に、おそらく国内外からの支持を得て、弟であるチャンドラ・シャムシェル・ラナがデヴ・シャムシェルに対する無血クーデターを行ない首相の地位を奪ったのである。デヴ・シャムシェルはわずか114日間在任しただけで首相の席を追われ、ダンクタに行った。その後、西ネパールに近いインドの丘陵地帯ムッソリーで晩年を送ったのである。
デヴ・シャムシェルは弟のチャンドラ・シャムシェルの陰謀を見抜いていたと言われている。しかし、彼は国民は自分の自由な政治思想を支持するだろうと信じていた。国民の支持さえ獲得することができれば、ライバルたちも彼に反する動きをすることはないだろうと考えた。そう信じて、改革計画を推し進めたのである。
1901年から29年まで首相を務めたチャンドラ・シャムシェル・ラナは、万人に教育の機会を与えるという考え5や社会を改革するためのプログラムには反対であったが、ネパールにおけるラナ家の支配を確固としたものにした、抜け目のないい支配者であり行政官でもあった。チャンドラ・シャムシェルはデヴ・シャムシェルが手をつけたいくつかの改革プログラムを実施した。8人の若者が日本に行くことも許可した。日本がアジアの強国となりつつあることに気づいていたのである。彼は1903年に、ネパールを二度目に訪れた河口慧海にも会っている。河口慧海はネパールを最初に訪れた日本人である。このとき、チャンドラ・シャムシェルは河口に「日本をこれほどまでに強くしたのは、何なのか」と質問した。河口は「教育、そして愛国心だ」と答えた。6