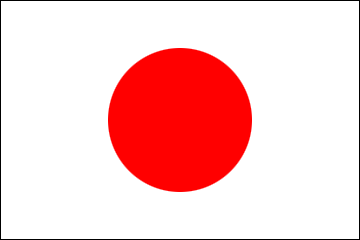菊田大使寄稿:ネパール大地震8周年に寄せて
令和5年5月3日
※これは、2023年4月25日付カトマンズ・ポスト紙に掲載された菊田大使による寄稿文の日本語訳です(英語版)。
2015年4月25日の正午前、ニューデリーの自宅で揺れを感じました。当時、私は在インド日本国大使館の次席でした。大使館の同僚に電話して震源地を確認したところ、インドではなくネパールであることがわかりました。安堵するどころか、地震の大きさに唖然としました。日本からの国際緊急援助隊のカトマンズ行きの特別便を調整するためにインド外務省に急いだことを今でも鮮明に覚えています。
ゴルカ地震後のネパールの国と人々の苦しみ、痛みは想像に難くありません。同時に、復興に尽力されているネパールの人々に心から敬意を表したいと思います。この機会をお借りして、被災者とそのご家族に改めてお悔やみを申し上げるとともに、震災後8年間にわたり日本が行ってきた様々な支援を振り返りたいと思います。また、事業の実施にご協力いただきましたネパール政府及び関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
日本は震災直後からネパールへの支援を開始しました。救助と医療サービスを提供するために災害救助隊が派遣されました。緊急援助物資に加えて、日本は国際機関や他の組織に緊急無償資金協力を提供し、大惨事に見舞われたネパールを支援するためにさまざまな緊急支援活動を提供しました。
こうした緊急支援に加え、日本はネパールの復興支援として、震災から2カ月後の2015年6月25日にカトマンズで開催されたネパール復興国際会議において、約2億6000万ドルの支援を表明しました。
この発表を受けて、2015年12月には、緊急学校再建プロジェクト(ESRP)および緊急住宅再建プロジェクトに対する有償資金協力に関する交換公文への署名が行われました。また、震災で被害を受けた橋梁や道路、病院等のインフラ復旧のための無償資金協力も導入されました。ESRPは2023年の今月4月、274に上る数の学校を再建してその使命を完了しました。日本は約束を守る国です。これらのプロジェクトは、単に施設を元の状態に戻すのではなく、ネパールの耐震性を向上させることを目的とした「ビルド・バック・ベター(より良く再建する)」のコンセプトに基づいて実施されました。
これら以外にも、日本は様々なスキームを活用して支援を行いました。その一例が、ネパールが誇る文化遺産の修復プログラムです。もう1つは、草の根人間の安全保障プロジェクトへの助成金です。これは、ネパールのNGOを含む非営利団体への返金不要の財政支援であり、到達するのが困難な遠隔地域社会における教育拠点の復活を支援します。NGOや地方自治体の活動を直接支援することで、地域社会のニーズに応える日本独自の援助方式です。
我々はまた、災害からの復興及び復旧のための強靭な計画の策定など、災害管理メカニズムの分野におけるネパールの制度的発展及び能力構築を支援しました。世界有数の災害多発国であり、自然災害のリスクが高いネパールにとって、将来の災害への備えは不可欠です。 また、地域住民自身が復興過程に参加することを求める住民参加型の技術協力プロジェクトも提供されました。
地震後の復興と再建への支援とは別に、ネパールの人々の間で広く知られているように、日本政府は何十年にもわたってネパールの大規模なインフラプロジェクトに貢献してきました。これらの新しく建設されたインフラプロジェクトにも、災害管理の側面があるということを指摘したいと思います。
例えば、現在進行中のネパール初の山岳道路トンネルプロジェクトであるナグドゥンガトンネル建設プロジェクトは、急増する交通量による交通渋滞の緩和や移動時間の短縮だけでなく、土砂崩れ事故やその他の自然災害のリスクを軽減することで、山岳地帯の安全性を向上させることが期待されています。
将来においては、発展を遂げたネパールがこれまでの復興プロセスの経験に基づき、より多くの費用と時間がかかるとしても、より強靭で耐久性のあるインフラと施設を構築するという考えを念頭に置いて、自ら公共事業を実施することが重要になるでしょう。
こうした復興支援、インフラ支援にとどまらず、私は教育や地域社会を通じて防災意識を高める方法について、日本の経験を共有できればと願っています。日本は、災害による被害の防止・軽減、緊急速報体制の確立、地域社会における災害情報の共有、防災教育の推進に力を注いでいます。 日本は、1923年9月1日の関東大震災を契機に、9月1日を「防災の日」と定め、防災の大切さを思い起こすため、今でも毎年この日に全国各地で避難訓練が行われています。
ゴルカ地震から今日で8年。ネパール政府だけでなく、地方自治体、地域社会、そしてネパールのすべての人々が、地震の経験から重要な教訓を学び続け、災害に強い国を確立するプロセスに参加する必要があると私は考えます。ネパールと同様に災害大国であり、たびたび災害に見舞われてきた日本も、地震やその他の自然災害の経験から多くの教訓を学んできました。100年前の関東大震災以来日本人がそうしてきたように、今日がゴルカ地震とその後の教訓をより良い未来に向けて思い起こす日になることを願っています。
そして、日本がネパール政府と連携して実施している数々の震災復興支援事業が、ネパールの復興・復興・強靭化につながるだけでなく、日本とネパールが長年にわたって培ってきた友好関係の一層の強化につながることを心から願っています。
ネパールがLDCカテゴリー(後発開発途上国)からの卒業を目指す2026年は、日本とネパールの国交樹立70周年でもあります。 その節目の年に向けて、両国関係が一層強化されることを心から期待しています。
「物理的な強靭さは重要、しかし人々の心と精神はもっと大切」
2015年4月25日の正午前、ニューデリーの自宅で揺れを感じました。当時、私は在インド日本国大使館の次席でした。大使館の同僚に電話して震源地を確認したところ、インドではなくネパールであることがわかりました。安堵するどころか、地震の大きさに唖然としました。日本からの国際緊急援助隊のカトマンズ行きの特別便を調整するためにインド外務省に急いだことを今でも鮮明に覚えています。
ゴルカ地震後のネパールの国と人々の苦しみ、痛みは想像に難くありません。同時に、復興に尽力されているネパールの人々に心から敬意を表したいと思います。この機会をお借りして、被災者とそのご家族に改めてお悔やみを申し上げるとともに、震災後8年間にわたり日本が行ってきた様々な支援を振り返りたいと思います。また、事業の実施にご協力いただきましたネパール政府及び関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
日本は震災直後からネパールへの支援を開始しました。救助と医療サービスを提供するために災害救助隊が派遣されました。緊急援助物資に加えて、日本は国際機関や他の組織に緊急無償資金協力を提供し、大惨事に見舞われたネパールを支援するためにさまざまな緊急支援活動を提供しました。
こうした緊急支援に加え、日本はネパールの復興支援として、震災から2カ月後の2015年6月25日にカトマンズで開催されたネパール復興国際会議において、約2億6000万ドルの支援を表明しました。
この発表を受けて、2015年12月には、緊急学校再建プロジェクト(ESRP)および緊急住宅再建プロジェクトに対する有償資金協力に関する交換公文への署名が行われました。また、震災で被害を受けた橋梁や道路、病院等のインフラ復旧のための無償資金協力も導入されました。ESRPは2023年の今月4月、274に上る数の学校を再建してその使命を完了しました。日本は約束を守る国です。これらのプロジェクトは、単に施設を元の状態に戻すのではなく、ネパールの耐震性を向上させることを目的とした「ビルド・バック・ベター(より良く再建する)」のコンセプトに基づいて実施されました。
これら以外にも、日本は様々なスキームを活用して支援を行いました。その一例が、ネパールが誇る文化遺産の修復プログラムです。もう1つは、草の根人間の安全保障プロジェクトへの助成金です。これは、ネパールのNGOを含む非営利団体への返金不要の財政支援であり、到達するのが困難な遠隔地域社会における教育拠点の復活を支援します。NGOや地方自治体の活動を直接支援することで、地域社会のニーズに応える日本独自の援助方式です。
我々はまた、災害からの復興及び復旧のための強靭な計画の策定など、災害管理メカニズムの分野におけるネパールの制度的発展及び能力構築を支援しました。世界有数の災害多発国であり、自然災害のリスクが高いネパールにとって、将来の災害への備えは不可欠です。 また、地域住民自身が復興過程に参加することを求める住民参加型の技術協力プロジェクトも提供されました。
地震後の復興と再建への支援とは別に、ネパールの人々の間で広く知られているように、日本政府は何十年にもわたってネパールの大規模なインフラプロジェクトに貢献してきました。これらの新しく建設されたインフラプロジェクトにも、災害管理の側面があるということを指摘したいと思います。
例えば、現在進行中のネパール初の山岳道路トンネルプロジェクトであるナグドゥンガトンネル建設プロジェクトは、急増する交通量による交通渋滞の緩和や移動時間の短縮だけでなく、土砂崩れ事故やその他の自然災害のリスクを軽減することで、山岳地帯の安全性を向上させることが期待されています。
将来においては、発展を遂げたネパールがこれまでの復興プロセスの経験に基づき、より多くの費用と時間がかかるとしても、より強靭で耐久性のあるインフラと施設を構築するという考えを念頭に置いて、自ら公共事業を実施することが重要になるでしょう。
こうした復興支援、インフラ支援にとどまらず、私は教育や地域社会を通じて防災意識を高める方法について、日本の経験を共有できればと願っています。日本は、災害による被害の防止・軽減、緊急速報体制の確立、地域社会における災害情報の共有、防災教育の推進に力を注いでいます。 日本は、1923年9月1日の関東大震災を契機に、9月1日を「防災の日」と定め、防災の大切さを思い起こすため、今でも毎年この日に全国各地で避難訓練が行われています。
ゴルカ地震から今日で8年。ネパール政府だけでなく、地方自治体、地域社会、そしてネパールのすべての人々が、地震の経験から重要な教訓を学び続け、災害に強い国を確立するプロセスに参加する必要があると私は考えます。ネパールと同様に災害大国であり、たびたび災害に見舞われてきた日本も、地震やその他の自然災害の経験から多くの教訓を学んできました。100年前の関東大震災以来日本人がそうしてきたように、今日がゴルカ地震とその後の教訓をより良い未来に向けて思い起こす日になることを願っています。
そして、日本がネパール政府と連携して実施している数々の震災復興支援事業が、ネパールの復興・復興・強靭化につながるだけでなく、日本とネパールが長年にわたって培ってきた友好関係の一層の強化につながることを心から願っています。
ネパールがLDCカテゴリー(後発開発途上国)からの卒業を目指す2026年は、日本とネパールの国交樹立70周年でもあります。 その節目の年に向けて、両国関係が一層強化されることを心から期待しています。