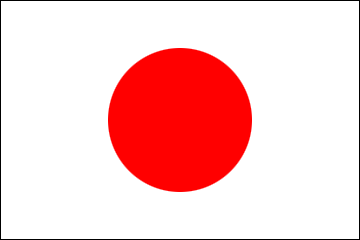菊田大使インタビュー:Kantipur 誌(2024年1月27日)
令和6年1月30日

これは、2024年1月27日発行のカンティプール紙に掲載された菊田大使のインタビューの日本語訳です。ネパール語の記事はこちらです。
(注)ネパール語インタビューのリード部が、日本はネパールにいかなる利害関係もなくとしている部分は、ミスリーディングな表現となっており、菊田大使の意図を正しく反映したものではありません。日本は、もちろんネパールとの友情を重視していますが、同時に、ネパールの発展、民主主義の進展及び平和と安定を期待しており、常にその旨のメッセージを発信しています。
(注)ネパール語インタビューのリード部が、日本はネパールにいかなる利害関係もなくとしている部分は、ミスリーディングな表現となっており、菊田大使の意図を正しく反映したものではありません。日本は、もちろんネパールとの友情を重視していますが、同時に、ネパールの発展、民主主義の進展及び平和と安定を期待しており、常にその旨のメッセージを発信しています。
大使インタビュー


ネパールと日本の関係は無私のものである。日本はネパールにいかなる利害関係もなく、良き友人としてネパールを支援している。両国は1956年9月1日に外交関係を樹立した。ネパールは1965年に東京に大使館を開設し、その2年後(注:実際は1968年)、日本はカトマンズに大使館を開設した。
以来、両国の友好関係にいささかの亀裂が生じたこともない。日本はネパールの主要な開発パートナーの一つである。カンティプールのJagdishor Pandayは、ネパールを支援し、愛してやまない国である日本の駐ネパール大使、菊田豊氏と対談した(抜粋)。
来るときは飛行機から素晴らしいヒマラヤ山脈が見えましたが、着陸すると霧とスモッグのせいでカトマンズから山々は見えませんでした。以前抱いていたイメージとは異なり、ネパールでは大気汚染が深刻な問題であることを知りました。 山、川、森の風景は私の故郷である日本の福島に似ていますが、当時満開だった美しい青いジャカランダはカトマンズ特有でした。
ところで、バヌバクタ・アーチャリヤさんに関連しての話ですが、日本にもラーマーヤナに似た民話があるのをご存知ですか? 物語の中で、主人公は猿や他の動物たちと一緒に鬼と戦うために島に行きます。
ところで、芸術的な意味ではありませんが、日本の格闘技界にアビラル・ギミレ(अबिरल घिमिरे)というネパール人の強いキックボクサーがいることをご存知ですか? 残念ながら彼のリングネームはアビラル・ヒマラヤン・チーターですが、ネパールにはチーターはいないと思います。日本人にとってはユキヒョウよりもチーターの方が馴染みがあるのかもしれません。あるいは、彼は背が高くて細いので、ずんぐりむっくりしたユキヒョウのようには見えないからかもしれません。とにかく、彼が強い日本人ボクサーに勝つのを見ると、気持ちがいいです。
以来、両国の友好関係にいささかの亀裂が生じたこともない。日本はネパールの主要な開発パートナーの一つである。カンティプールのJagdishor Pandayは、ネパールを支援し、愛してやまない国である日本の駐ネパール大使、菊田豊氏と対談した(抜粋)。
1.初めてネパールに来たのはいつですか。ネパールの地理についてどう思いますか。
私は2005年5月に東京外務省のネパール担当課長として初めてネパールを訪問しましたが、トリブバン空港から直接多目的武道センター(MMAC)にネパール人剣道選手達との稽古に行きました。後日、大使館の医務官から、高山病の危険があるのでそのようなことはしないようにと忠告されました。その時、カトマンズがいかに高い場所にあるのかを実感しました。来るときは飛行機から素晴らしいヒマラヤ山脈が見えましたが、着陸すると霧とスモッグのせいでカトマンズから山々は見えませんでした。以前抱いていたイメージとは異なり、ネパールでは大気汚染が深刻な問題であることを知りました。 山、川、森の風景は私の故郷である日本の福島に似ていますが、当時満開だった美しい青いジャカランダはカトマンズ特有でした。
2.ネパールでのご活動中には多くの人にお会いになると思いますが、ネパールの人々についてどう思いますか。
人々は控えめでフレンドリーです。私はネパールに大使として駐在できていることを幸運に思います。大使館の現地職員を含め、日本語をとても上手に話すネパール人にたくさん会って感銘を受けました。ネパール人全般に対する私の印象は、似ているけれど異なる組織がたくさんあり、それぞれのネットワークで活動しており、統一されていないということです。それはこの国の多様性によるものかもしれません。3.ネパールの天気についてどう思いますか。
カトマンズの気候はかなり快適です。しかし、夏はモンスーンの季節が長く、冬は霧の多い季節が長いため、外国人旅行者にとって観光シーズンはかなり限られています。 日本人観光客は秋のお祭りシーズンや春の花の季節を狙って慎重に旅程を組まなければなりません。4.ネパールの食べ物についてはいかがですか。一番好きなものを教えてください。
柿、栗、ニジマス、イチゴなどはもともと日本にあったものであり、人々の強い絆によってこの国にもたらされています。なので、ネパール料理同様、当然それらの食べ物も好きです。 ダルバート、モモ、チョーミンなどの代表的なネパール料理のほかに、ネパール料理と呼んでいいのかわかりませんが、チベット料理のギャコクやネワール料理も好きです。ヨマリの形も味も好きです。ジュジュダウの味は最高です。5.ネパールの習慣についてどう思いますか。
ネパールの人々の習慣には日本人との類似点がたくさんあることに気づきました。年長者への敬意、来客者へのおもてなし、家族の価値観、控えめな人間性、自然の恵みに感謝する季節の祭りなどはほんの一例です。ネパール人がナマステと言うときに、掌を前に合わせるのを見るのも好きです。ネパール人ほどではありませんが、私たち日本人もお寺や神社に参拝するときは合掌します。6.ネパールのお祭りについてどう思いますか。ネパールのお祭りをお祝いしますか。
日本の神道は自然を崇拝する一種のシャーマニズムです。私たち日本人は、自然を征服しようとするのではなく、自然とともに生きることを好みます。私たちには太陽の神、雨、風、雷、あらゆるものにそれぞれ神がいます。私たちは木、岩、山、あらゆる自然の畏敬の念を抱かせる物体を神聖なものとして崇拝します。そういう意味では、ネパールのお祭りと似ている部分がたくさんあります。仏教寺院の重塔も似ています。祭り囃子も似ています。私たち日本人はネパールの人々と精神的な価値観を多く共有していると思います。私は、家族と一緒にその年の豊作を祝う秋の日本のお祭りが好きです。そういう意味で、私はここのダサイン祭りが好きです。また、私はかつて大使館の次席としてニューデリーに滞在していたので、ホーリーやディワリなどのヒンドゥー教のお祭りは馴染みがあります。7.ネパール語をお話しになりますか。ネパールには何言語が存在するかご存じでしょうか。
初級レベルのみです。将来ネパールに赴任することが分かっていたら、インドにいる間にデーヴァナーガリー文字(देवनागरी)をもっと真剣に学ぶべきだったと思います。ただ、語順や多くの文法は日本語と同じなので、ネパール人が話したり書いたりする際の脳の働きはある程度理解できます。2011 年の国勢調査によれば、ネパールには 123 の言語があったと承知していますが、その数は減少しており、多くの言語が消滅の危機に瀕しています。ネパールの人々は社会の近代化と伝統文化の保存の間で難しいバランスをとらなければなりません。8.ネパール音楽をお聞きになりますか。具体的に好きな曲はありますか。
私はサヤ・トゥンガ・プルカ・ハミ(ネパール国歌)を諳で歌えます。この歌は、この国の多様性をよく表していると思います。昨年、ネパティア(नेपथ्य)が日本ツアーを大成功させたとき、近年日本に於ける存在感を増している在日ネパール人たちがコンサートホールに集まり、歌い、踊り、叫び、ネパール国旗を振っている姿を見てうれしく思いました。9.ネパール文学についてもご存じでしょうか。
私はアーディカビ・バヌバクタ・アーチャリヤ(आदिकवि भानुभक्त आचार्य)やマハカビ・ラクシュミ・プラサド・デーヴコタ(महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा)のような有名な名前を知っています。但し、ネパール語で彼らの作品を読むのは外国人の私には不可能です。プラティヴァ・ラナ元駐日ネパール大使の詩集『マヤのカーテン』の英語版を読んだ時は、政治家や外交官としてではなく、心の奥底で愛と国家を想う、誠実な一人の人間としての彼女の人間性に触れて驚きました。ところで、バヌバクタ・アーチャリヤさんに関連しての話ですが、日本にもラーマーヤナに似た民話があるのをご存知ですか? 物語の中で、主人公は猿や他の動物たちと一緒に鬼と戦うために島に行きます。
10.ネパール映画をご覧になったことはありますか。
私は2005年頃のこの国の状況を知っているので、カースト制度と「反乱」について考えながら、重い心で『黒い鶏(カロ・ポシ)』を鑑賞しました。最近の映画の中では、『ハルカラ』(हल्कारा)は、現在の出稼ぎ労働者の大量流出を思い起こさせる、心の痛む物語です。必ずしもネパール映画というわけではありませんが、ネパールで撮影された日本人や他の映画制作者による良い映画がたくさんあります。日本大使としては、2015年のゴルカ地震の際の日本の救助隊を描いた『わが愛(カトマンズの約束)』に触れておきたいと思います。私は昨年上映されたイタリア映画『八つの山(Le otto montagne)』が好きです。映画の中では、ネパール人が語った、須弥山をはじめとする八つの山の概念が重要な役割を果たしています。11.ネパール国内では何カ所を訪問されましたか。なかでもお気に入りの訪問地について教えてください。
イラムの茶畑の光景はとても美しかったです。ポカラのサランコットでは、今の天皇陛下が皇太子時代にこの地を訪れ、マチャプチャレ山と村の女性たちの写真を撮られたことを思い出しました。私は2005年に釈迦誕生をモチーフにした木彫りの銘板を頂いたことがあるのですが、昨年ルンビニを訪れ、仏陀誕生の場所に立ったとき、私は「18年経って遂にここに来た」と心の中で思いました。12.最後に、ネパールの芸術と文化についてはどう思いますか。
高級レストランやホテルで外国人観光客向けに披露される商業化されたダンスよりも、お祭りで地元の人たちが自分たちで踊ったり音楽を演奏したりするのを見るのが好きです。バクタプルの孔雀の窓やその他の木の彫刻作品は素晴らしいです。ミティラの絵は可愛いです。ところで、芸術的な意味ではありませんが、日本の格闘技界にアビラル・ギミレ(अबिरल घिमिरे)というネパール人の強いキックボクサーがいることをご存知ですか? 残念ながら彼のリングネームはアビラル・ヒマラヤン・チーターですが、ネパールにはチーターはいないと思います。日本人にとってはユキヒョウよりもチーターの方が馴染みがあるのかもしれません。あるいは、彼は背が高くて細いので、ずんぐりむっくりしたユキヒョウのようには見えないからかもしれません。とにかく、彼が強い日本人ボクサーに勝つのを見ると、気持ちがいいです。